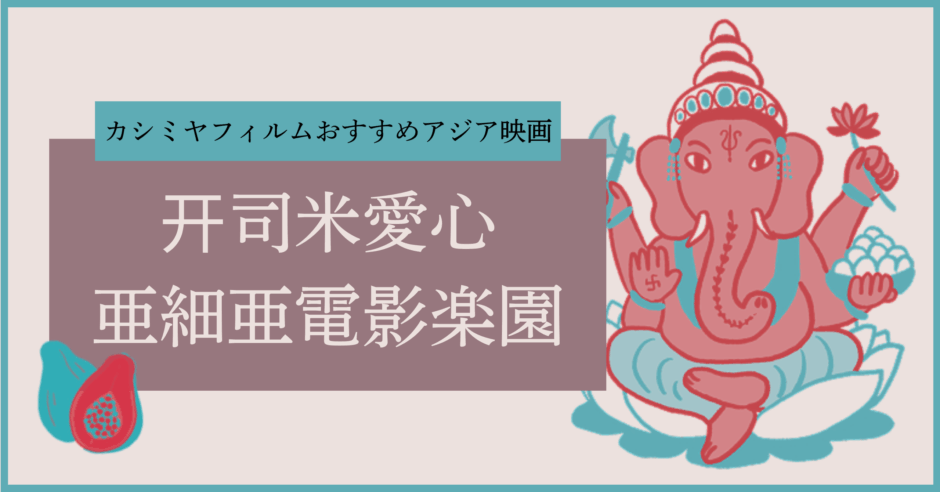台湾映画『ヤンヤン 夏の想い出』は、エドワード・ヤン監督が2000年に完成させた長編映画であり、家族という最小単位を通して、人が生きる時間そのものを静かに、しかし深く見つめた作品である。本作がカンヌ国際映画祭で高い評価を受けたことはよく知られているが、その穏やかな語り口の背後には、監督自身の切実な死生観が確かに刻み込まれている。ヤンはこの映画の完成前後から癌を患っており、『ヤンヤン 夏の想い出』は結果的に彼の遺作となった。その事実を踏まえて観ると、この映画が放つ静かな光は、より一層、胸に迫ってくる。
物語は、台北に暮らす中産階級の一家の日常を軸に展開していく。祖母の倒れる場面から始まり、父・NJの仕事と過去の恋、母・ミンミンの精神的な揺らぎ、思春期を迎える娘・ティンティンの戸惑い、そして小学生の息子・ヤンヤンの素朴な問い。それぞれのエピソードは大きな事件を伴うわけではないが、人生の中で誰もが一度は直面する「選ばなかった可能性」や「理解できない他者との距離」が淡々と描かれていく。
エドワード・ヤンの演出は、徹底して説明を排する。登場人物たちは自分の感情を多く語らず、カメラもまた彼らを過剰に追いかけない。その代わり、フレームの中には「時間」が流れている。仕事に追われる日常、すれ違う会話、何気ない沈黙。その積み重ねが、人生の重みとして観る者の前に現れてくる。ヤンは、ドラマティックな瞬間よりも、人が生きている「途中」の時間にこそ意味があることを、静かに示している。
特に印象的なのは、息子ヤンヤンの存在だ。彼は「自分の目では見えない、後ろ側を人に見せてあげたい」と言い、街中の人々の後頭部を写真に撮り続ける。その行為は、子どもらしい純粋さであると同時に、この映画全体を貫く重要なメタファーでもある。人は自分のすべてを知ることができない。他者の視点を通して初めて、自分という存在の輪郭が浮かび上がる。その不完全さをヤンは否定するのではなく、むしろ人間らしさとして肯定している。
父・NJの物語もまた、過去と現在の間で揺れる人間の姿を象徴している。若き日に別れた恋人との再会は、「もしも」の人生を一瞬だけ立ち上がらせる。しかしNJは、その可能性に完全に身を委ねることはしない。彼は過去を取り戻すことも、現在を否定することもできないまま、それでも前に進むしかない。その姿は、人生が常に未完成であり、選択とは喪失を伴うものであることを痛切に語っている。
母・ミンミンが精神的な疲弊から宗教的な場へ身を寄せるエピソードも、本作の死生観と深く結びついている。彼女は「自分がいなくなっても世界は変わらない」という事実に直面し、その虚無に耐えきれなくなる。しかし同時に、その感覚は「それでも生きている」という現実を浮き彫りにする。エドワード・ヤンは生の意味を大げさに語らない。意味が分からないままでも、人は生き続けるしかないという事実を淡々と受け止めている。
祖母の昏睡と、最後に訪れる死は、この映画に明確な「終わり」を与えるが、それは悲劇としてではなく時間の自然な帰結として描かれる。そして葬儀の場でヤンヤンが読み上げる弔辞は、この作品の核心に触れている。「おばあちゃん、僕はまだよく分からないことがたくさんあるよ。だから大きくなったらなりたいと思うんだ。人の知らないことを教えてあげたり、見たことのないものを見せる人に。きっと毎日すごく楽しいと思うよ。」その言葉は、まるでエドワード・ヤン自身の遺言のようにも響く。
完成当時、死を意識していたであろうヤンにとって、『ヤンヤン 夏の想い出』は、人生を総括する作品であったのかもしれない。しかしそこには、絶望や諦観よりも、静かな受容がある。人生は完全には理解できない。それでも、人は誰かと関わり、時間を共有し、記憶を残していく。その営み自体が、生きることの意味なのだと、ヤンはそっとこちら側に差し出す。
『ヤンヤン 夏の想い出』は、大きな感動を押しつける映画ではない。だが、観終えた後に日常の風景が少しだけ違って見えるようになる。その変化こそが、この映画が持つ力であり、エドワード・ヤンが最期に私たちに託した、静かで確かなメッセージなのだと追想する。
作品紹介
ヤンヤン 夏の想い出
監督:エドワード・ヤン 製作年:2000年 製作国:台湾、日本
上映時間:173分 配給:ポニーキャニオン
ヤンヤンは祖母や両親、姉のティンティンと台北に住んでいる、ごく普通の家庭の少年。ところが、叔父の結婚式を境に、様々な事件が起こり始める。祖母は脳卒中で昏睡状態となり、母は精神不安定となって新興宗教に走り、父は初恋の人と再会して心を揺らす。姉は隣家の少女のボーイフレンドと交際を始めてしまう。そして、ヤンヤンにも幼い恋心が芽生え始める……。「クーリンチェ少年殺人事件」のE・ヤン監督が現代の家族が抱える様々な問題を瑞々しくリアルに描いた作品。