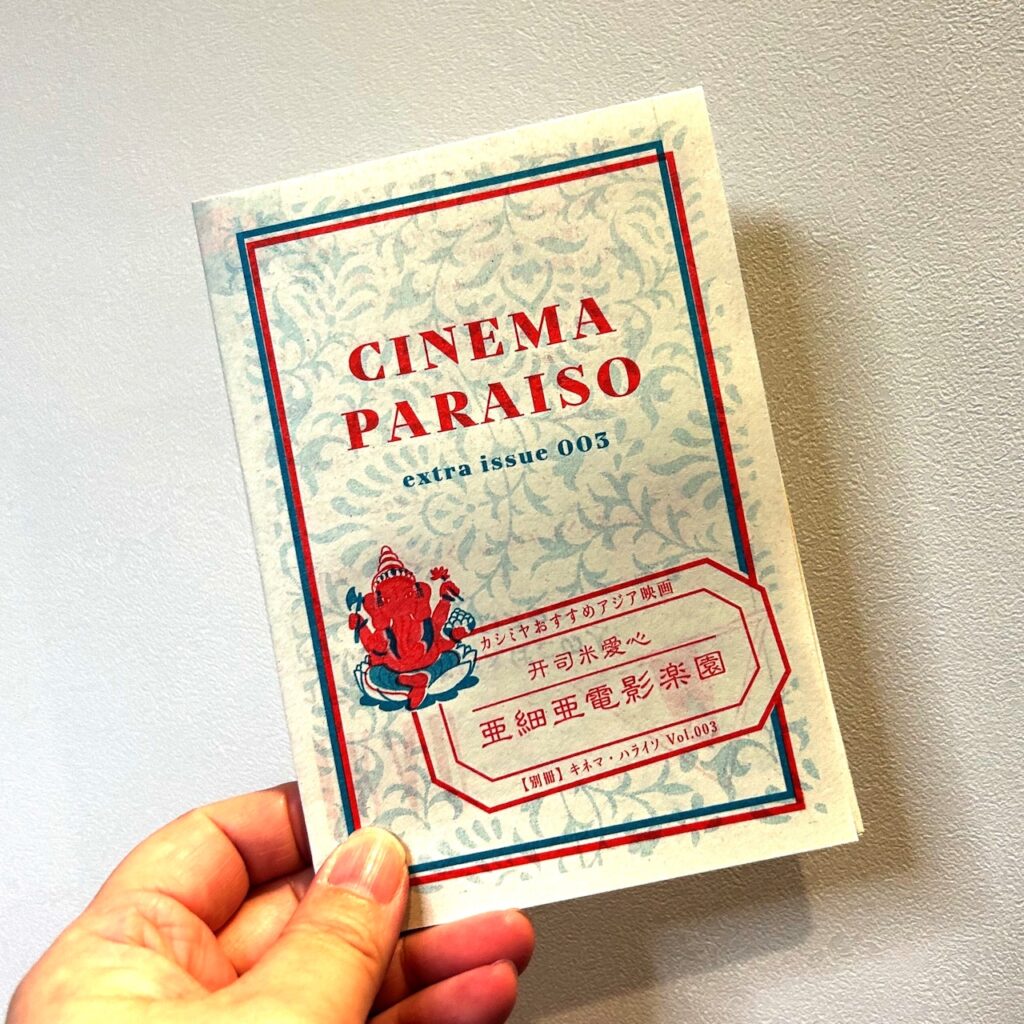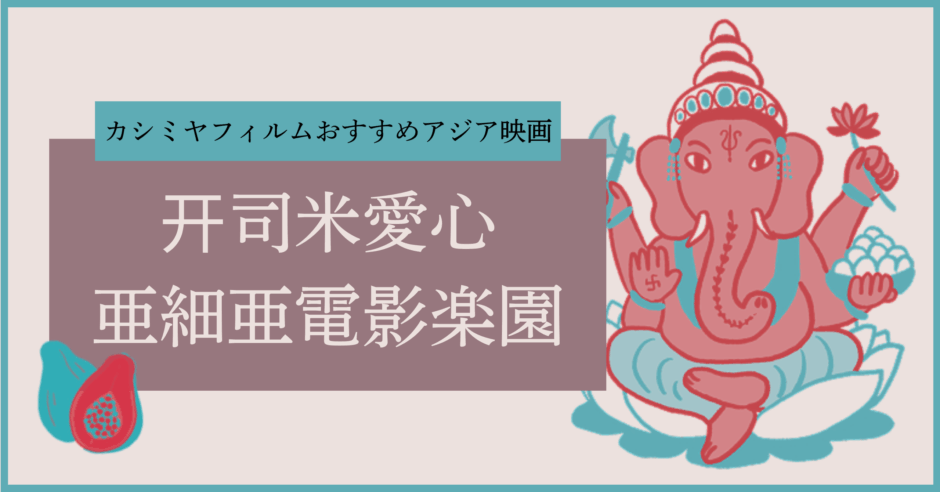パヤル・カパーリヤー、インド・ムンバイ出身の女性監督。それ以外の情報のないまま、彼女の最初の長編劇映画作品『私たちが光と想うすべて』に出会った。作品に関する情報でさえ、劇場で観た予告編 と、2024年カンヌ国際映画祭でのグランプリ作ということ以外は、ほぼない。
いい映画や音楽に出会う時、どこか得体の知れない違和感をともなう場合がある。経験則が増えてくるにつれ、たいていそれが自分にはない未知の要素の体験と興味のはじまりなのだと気付く。
しかし、この映画の鑑賞体験については、初見での違和感が、未経験要素からのものではないな、と感じた。そして、安易に言語化したくはないなという感情。上手く言えないが、”近くて遠い何か”を咀嚼できないもどかしさが残った気がする。
映画は、通勤ラッシュ、人混みの駅、電車内のシーンから始まる。しかも雨季のムンバイは足元が悪い。自分の日常なら憂鬱でしかない。不快指数さえともなう想像は客席の自分を実際憂鬱な気分にさせている。
雑踏、スマートフォン、インタビュー音声。都市について。
病院、多産について相談に来る女性。働く女性、ひと息つく彼女、恋人からのチャット。彼女の無邪気さを音符にしたようなに踊るピアノ。聴きおぼえのあるそれはエチオピアの修道女でもあるエマホイ・ツェゲ=マリアム・ゴブルーによる楽曲。
それほど広くはない部屋、離れ離れになっている夫の話、同居人に隠している秘密。結婚に関するインドの現在と、女性たちが都市で生活する上での問題の数々。
ひとつずつ噛むようにシーンを味わうことで、メッセージを含む作り手の意図を愛でることができる映画、それを、彼女のデビュー作『何も知らない夜』という実験映画を観た後の、二度目の『私たちが想うすべて』でわかった。あるいは、作家性の合点が”叶った”と言うべきか。そして、この監督は、なまやさしい作家ではないなという確信も持った(あるインタビューで「典型的メロドラマ」と今作を自嘲していたが外向けの物言いだろう)。
インドでは現代的な民主化への急発展と矛盾するカーストや他宗差別が根強いと聞く。今世紀の、アジア各国やいわゆるBRICS各国の都市部の開発ブームは、”戦後とバブルが同時にきたようなもの”と例えられるが、名目上のGDPが日本と競るインドの都市部でも、経済格差や教育事情に混沌を孕んだまま発展が加速していることは想像に難くない。作品冒頭の映像とインタビュー音声、作中のエピソードの諸々は、悪天候のイメージに助長され、それらを想起させるにじゅうぶんな”違和感”を感じられた。ムンバイを訪れたことのない自分にさえ、雑多なまま育ってしまった街に暮らすことへの、ある種の諦念に近い不快感は、訪れたことのあるどこかの都会の夜に置き換えた記憶、フラッシュバックのような経験的リアルとして感じられるのだ。
監督は、取り回しのきく小型機材を多用し、都市部の夜や室内でのシーンを中心に構成することで、影と闇を作り出し、青いミスト・フィルターによってその”美しくはない実像”をフィルムの暗部に、湿度の滲みを加えてひっそり描いてみせた。『何も知らない夜』で焼き付けられた過激さを含むリアルは、今作の”影”になり、”光”の副産物になる。いや逆に、”影”を想像させることで”光”を見せたのかも知れない。自分は、それを”美しい映像”と感じることに感情的な違和感を持ったのだと時間が経ったいまはわかる。
彼女たち自身の抱える問題、先延ばしにしていること、多言語、求愛、社会制度と慣習。旅、森の中の洞窟、自由の希求。そして、はからずも訪れる小さな変化のきっかけ。
彼(か)の国のタブーを前提として観ると、監督が描いたいくつものカットは、かなり攻めた仕事になるのだろう。それを考えてしまうと別の痛みが感情の邪魔をする。そこを踏まえて、恋愛&シスターフッド映画として受け入れるハードルをカパーリヤー監督は用意している。そこが、彼女の”生やさしくない作家”という印象になる。
とはいえ、ひとりの人として彼女たちの表情だけを注視すると、「同じなんだな」とも思う。どんな環境にいてもどんな身の上であっても、人間の持ついくつかの感情の種類は同じなのだ。まるっきり自分たちに置きかえて感情移入することはできなくても、実直さを持った作品には、少しの共感できる部分だけからも伝えられる力がある。たとえ物語が結果を見せなくても、”せつなさ”や”わずかな期待感と戸惑い”といった繊細で、最もこの作品にとって大事な、パーソナルな部分をスクリーンから受け取ることができる。やはり情緒的な表現においてもカパーリヤー監督は、映像によって伝える術に長けているとしかいいようがない。生やさしくはない優しさ。
最後のシーン、粗末なビーチバーにいくつもの原色の灯りが点る。毎日一緒だった彼女たちそれぞれの、知らない一面、別の顔を光が揺らす。それは、登場人物たちの感情のフェーズ。
決め台詞はない。そして、それぞれの生きづらさの中でそれぞれの生活は続いていくのだろう。秀逸なタイトル通り(おそらく掛詞的に、映画というアートフォームそのものを現す)、すべてのものごとはimagineすることで、その照度や温度を変える。いつのまにか、彼女たちの旅の日々に帯同している客席の自分がいた。
この映画を、上手く言語化することはやはり自分には難しい。何故なら、一切無駄のないシナリオやカット割りと音響処理、時間をかけた映像のルックによって、説明的にならない点も含め、映画がすべてを語っているように思えるからだ。一度目に観た時に、咀嚼を躊躇した”近くて遠いなにか”は、自分の日常の、不快と思うものの既視感、あるいはそれと真逆な、”自分は慎ましくも幸福である”という安堵感、それがいかに貴重かという普遍的な問いだった。ありふれたそれを”光”と呼んでもいいのかも知れない。

コラムを情緒的に締めることを照れずに告白すれば、『何も知らない夜』から続きの回で観た『私たちが光と想うすべて』、エンドロールの最中、この作品を擬人化して、こんな言葉をかけたい感情が何故だか湧いてきた。
I’m so proud of you.
誇り。ポリティカルでありながら、とてつもなく詩的な映画作家にしばらくぶりに出会えた喜びを抱えて夜の街に出ると、様々な言語の会話が飛び込んで来る。雑多に変わり続ける蒸し暑い東京という都市を少しだけ許せる気分になっていた。

『私たちが光と想うすべて』
配給:セテラ・インターナショナル
2024年製作/118分/PG12/フランス・インド・オランダ・ルクセンブルク合作
インド映画として初めて第77回カンヌ国際映画祭グランプリを受賞したドラマ。ムンバイで働く看護師のプラバとルームメイトのアヌは、それぞれ親が決めた結婚や、家族に反対される恋人との関係など、ままならない現実に葛藤しています。
ある日、立ち退きを迫られた同僚パルヴァディを故郷の海辺の村へ見送る旅に出た二人は、神秘的な別世界のような村で、自分たちの人生を変えるきっかけとなる出来事に遭遇します。光に満ちた映像美と幻想的な世界観で、自由に生きたいと願う女性たちの友情と決意を描いた、パヤル・カパーリヤー監督の長編劇映画デビュー作です。
【別冊】キネマ・ハライソ Vol.003 カシミヤおすすめアジア映画特集|开司米愛心亜細亜電影楽園
アジアの中でも映画がアツい7ヶ国(台湾・韓国・中国・香港・インド・イラク・ベトナム)のオススメ映画を掲載
掲載作品:花様年華/重慶森林/堕落天使/春光乍洩/2046/ペパーミント・キャンディー/カップルズ/百年恋歌/トゥクダム 生と死の境界/青の稲妻/長江哀歌/大樹のうた/青いパパイヤの香り/シクロ/夏至/そして人生はつづく/風が吹くまま
■参加クリエーター
コラム:shin/はるこ/kawamitsu/やすよ/mint/piiiyaaa/中原 陸/ぶぶ漬け イラスト:ふせ こに デザイン:エータ